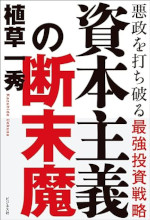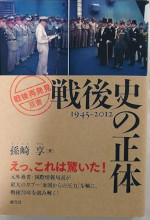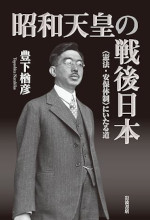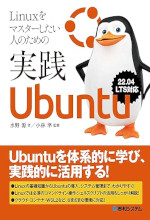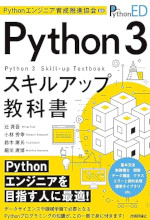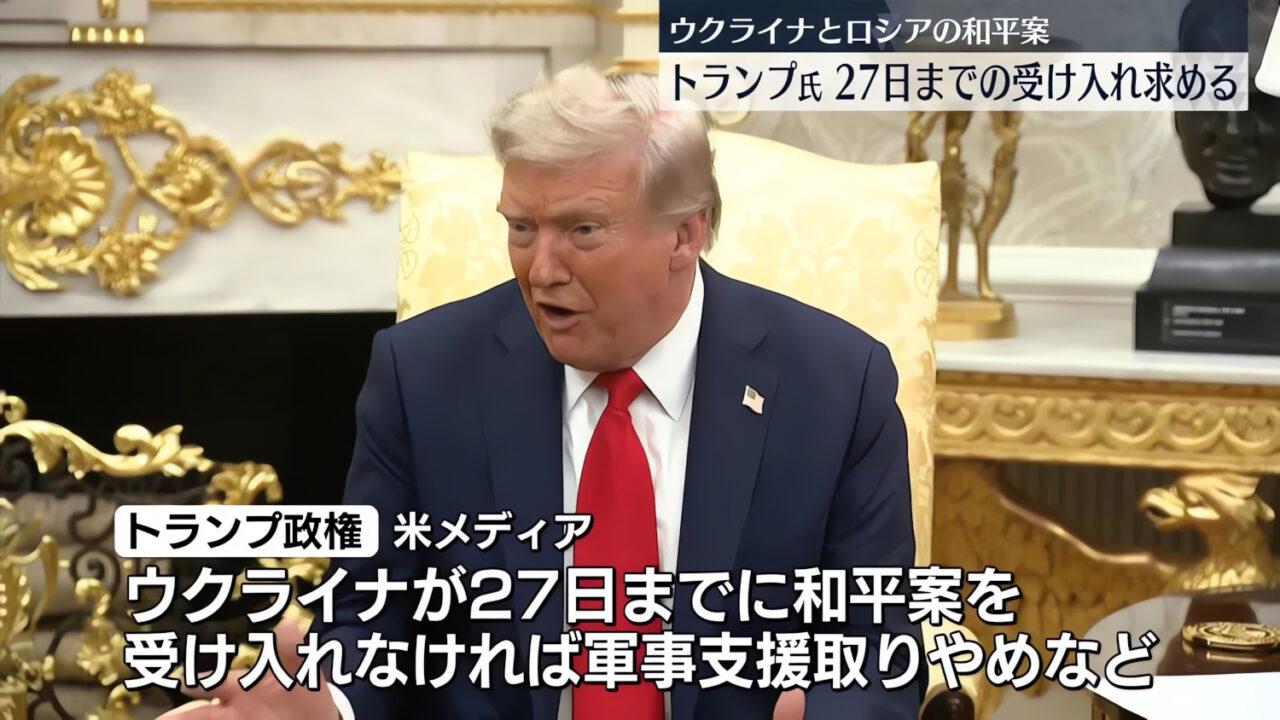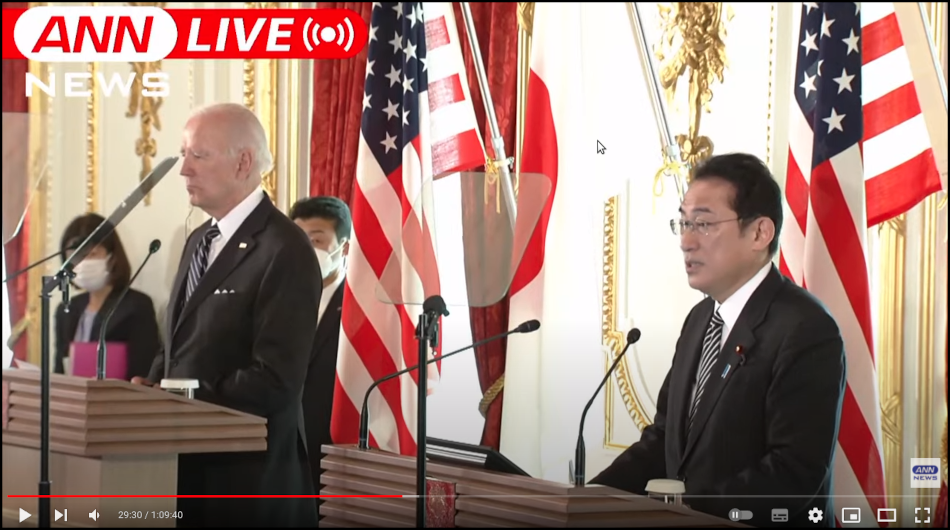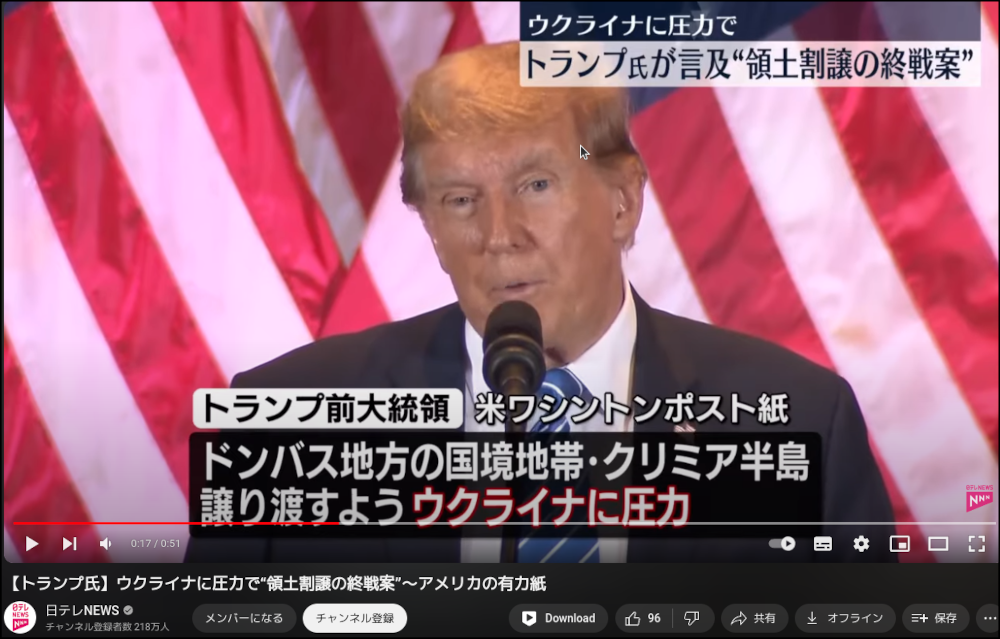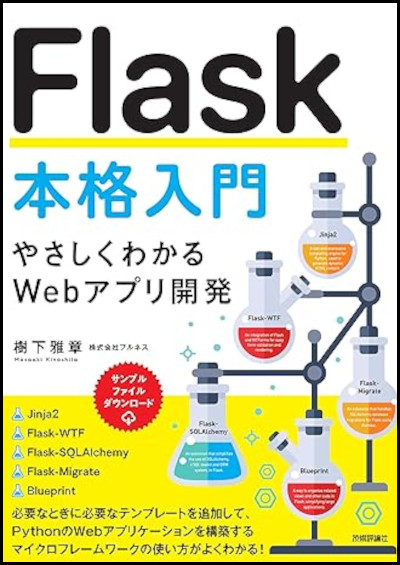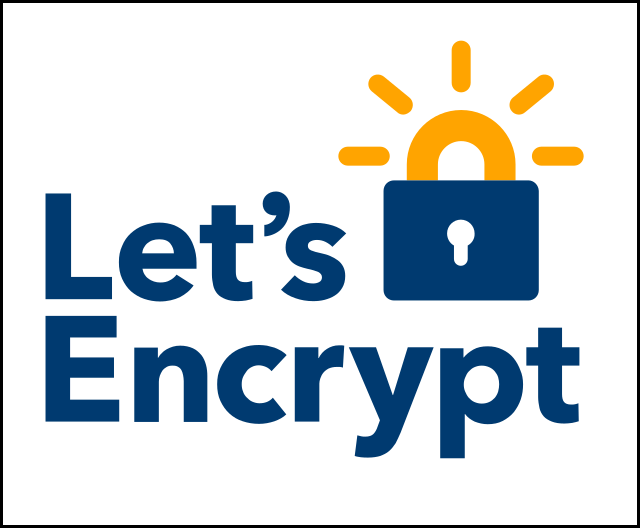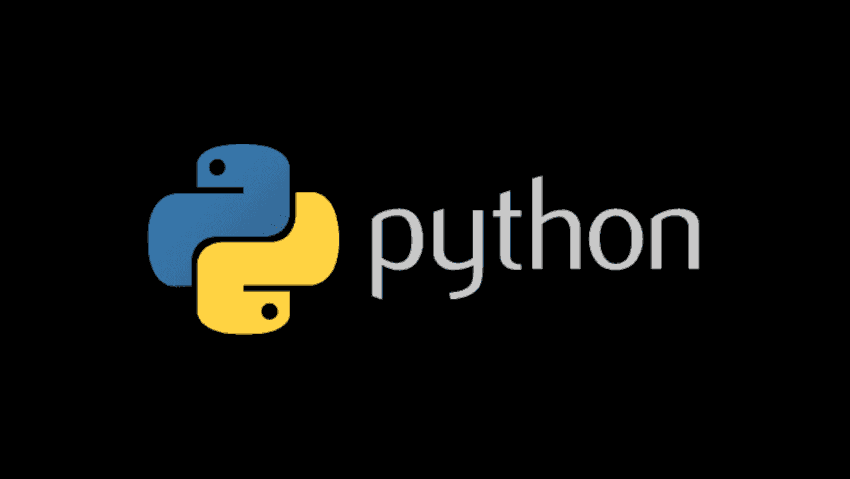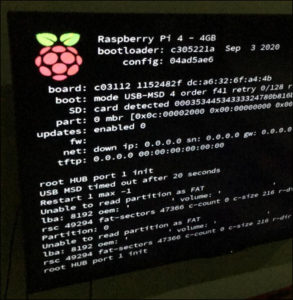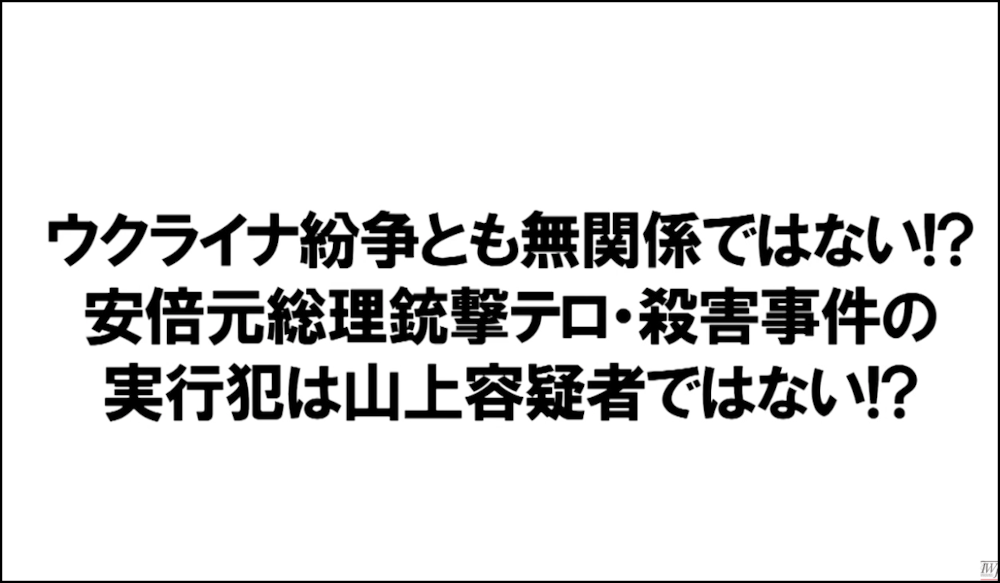高市早苗首相の「台湾有事は日本有事で自衛隊を派遣する」との答弁は大失策ー多極化推進外交に大転換が不可欠
高市首相は今のところ、単なる「反共右翼主義者」で、世界が冷戦体制から多極化体制に大転換していることを知らないようだ。これに関して、サイト管理者(筆者)は有力AIシステムのCopilotとチャットを行った。一部を抜粋する。
(注:ゼレンスキー政権は「戦況悪化」「支援縮小」「国内疲弊」という三重苦に直面しており、現状のままでは再起不能に近い状態と評価する見方は十分に根拠があります。今後は「挙国一致内閣」や「戦後処理体制」への移行が現実的シナリオとして浮上してくるでしょう)そういう世界の激変からみて、高市早苗首相は、反共右翼路線のままで良いとは思わない。多極化外交に転換すべきではないか。
ご指摘の通り、世界が「民主主義 vs 共産主義」という単純な対立から、米中G2を軸とした多極化構造へと移行している現状を踏まえると、日本の外交戦略も従来の「反共右翼路線」だけでは限界が見えてきます。高市早苗首相(仮定)の立場を想定すると、以下のような課題と転換の方向性が浮かび上がります。
🇯🇵 日本外交の課題
・日米同盟依存の限界 米国が台湾防衛を曖昧にし、ウクライナ支援も縮小する中で、日本が「米国一辺倒」で安全保障を語ることはリスクを伴います。
・日中平和友好条約との矛盾 「台湾有事は日本有事」と強調すれば、条約の精神と緊張を生み、外交的柔軟性を失います。
・経済安全保障の多元化 半導体や資源供給をめぐる競争の中で、米国だけでなくEU・インド・ASEANとの連携も不可欠です。🌍 多極化外交への転換の方向性
・多層的安全保障 米国との同盟を基盤にしつつ、欧州・インド・豪州・ASEANとの安全保障協力を強化。
・経済連携の多元化 半導体・エネルギー・AI技術などで、台湾・韓国・ASEAN・インドとのサプライチェーンを再構築。
・中国との限定的対話 対立一辺倒ではなく、気候変動・経済交流など限定的分野で協力を模索し、緊張緩和の余地を残す。
・価値外交から現実外交へ 「反共」というイデオロギー的立場よりも、「多極化の中で日本の利益を最大化する」現実的外交へシフト。🧭 まとめ
高市首相が仮に「反共右翼路線」を維持すれば、米国依存と中国敵視に縛られ、日本の外交余地は狭まります。むしろ、多極化外交に転換し、複数の極と柔軟に連携することで、日本は主体的な安全保障と経済戦略を確立できると考えられます。
もともと、「台湾防衛」は戦争省のエルブリッジ・コルビー次官(政策担当の俊才)が日本とオーストラリアに働きかけたものだ。しかし、コルビー次官はトランプ大統領にウクライナ支援を止めるように進言した実績がある。トランプ大統領も米中関係を「G2」と呼び、バイデン前大統領とは異なって再び、台湾に対して「曖昧外交戦略」を採用しているし、コルビー次官自身も米国が台湾を守ると明言していない(https://www.youtube.com/watch?v=hNHXXBlCj7I&t=788s)。

米中問題の本質は、台湾のコンピューター産業のハード、ソフトの問題、もう少し端的に言えば、AI用の超高性能半導体製造技術とAIソフトにある。この点では、台湾は世界最高性能の台湾積体電路製造(TSMC)を保有しており、その会長は国民党党員のモーリス・チャン氏だ。そして、AppleやAMD、ARM、NVIDIA(株式時価総額は5兆ドルで、日本の国内総生産よりも大きい)などのファブレス企業が製造を委託している。

NVIDIAのジェン・スン・ファン最高経営責任者(CEO)も中華系米国人(中華民族)である。また、旧西側諸国ではOpenAIが生成AIを開発したが、中国も負けじとオープン・ソース(ソースコードが開示されて、自由に改変できるソフト)で、画期的なDeepSeekというAIソフト(会社名でもある)を作った。会社(有限公司)を創設した人物は、若干40歳の梁文峰(Liang Wenfeng)氏である(https://prebell.so-net.ne.jp/feature/pre_25021002.html)が、実際にAIソフトを開発した人物は天才女性エンジニアの羅福莉(Luofuli / ラ・フーリー)氏である(https://x.com/masahirochaen/status/1885858368755286070)。

第三次産業革命は、ハード、ソフト両面でのAI技術が火をつけると言われる。中華民族が最先端を走っているのは事実だ。中国の習近平国家主席も、そういうハード、ソフト両面でのAIを中心とした台湾のコンピューター産業を軍事力で破壊する気はさらさらないだろう。ここで、台湾の政治状況をCopiloとのチャットからまとめてみる。
要点まとめ: 台湾国民党の対中外交政策は、基本的に「融和・対話路線」を重視し、中国との緊張緩和を目指す一方で、台湾の安全保障や国内世論とのバランスに苦慮しています。近年は「九二共識」(注:)を基盤に、中国との経済・政治的交流を推進する姿勢が鮮明です。
注:「九二共識とは、中華人民共和国と中華民国の当局間で『一つの中国』問題に関して達成したとされる合意の通称である。 名称は、中国側窓口機関海峡両岸関係協会と台湾側窓口機関海峡交流基金会が、1992年に香港で行った協議に由来し、2000年4月に台湾の行政院大陸委員会主任委員蘇起が名付けて公表した」(Wikipedia)🇹🇼 国民党の対中外交政策の特徴
・九二共識の支持
国民党は「一つの中国」を前提にしつつ、両岸がそれぞれ解釈を持つ「九二共識」を外交の基盤としています。これにより、中国との公式・非公式対話を可能にする立場を維持しています。
・融和・対話路線
現主席(注:党首)の鄭麗文氏は、中国本土との「統一志向」を鮮明にし、習近平から祝電を受けるなど、中国側も国民党への接近を強めています。これは民進党の「現状維持・防衛強化路線」と対照的です。
・国防費増額への反対
民進党政権が国防費をGDP比5%まで引き上げる方針を示す中、国民党は「国防よりも社会福祉に予算を回すべき」として防衛費増額に反対する傾向があります。
・経済交流の重視
国民党は中国との経済的結びつきを強化することで、台湾の安定と繁栄を確保できると主張しています。特に貿易や投資の拡大を通じて「平和的発展」を目指す姿勢が強いです。🧭 まとめ
台湾国民党の対中外交政策は「九二共識を基盤にした融和・対話路線」であり、経済交流を通じて平和を維持しようとしています。しかし、国内世論や国際環境とのズレ、そして中国の強硬姿勢が大きなリスク要因となっています。
📊 台湾主要政党の支持率(2025年9月時点)
政党 支持率 傾向 民進党 30.9% 前回比 +1.5pt、依然トップ 国民党 25.2% 前回比 +5.1pt、異例の急伸 民衆党 14.4% 前回比 -0.8pt 時代力量 1.9% 微減 その他政党 0.9% 微小勢力 無党派層 26.1% 中立層が依然大きい 🔎 支持率上昇の背景
・大規模リコール運動の失敗
民進党に打撃を与えた「大罷免」(注:https://www.spf.org/spf-china-observer/document-detail074.html)失敗の影響で、国民党が「反動的支持」を得たと分析されています。
・野党連合の可能性
国民党(藍)と民衆党(白)の合計支持率は約39.6%に達し、民進党との差は8.7ポイント。野党協力が現実化すれば政局に大きな影響を与える可能性があります。
・有権者心理の変化
民進党への失望感が一部で広がり、国民党が「受け皿」として支持を回復している状況です。🧭 展望
国民党は依然として「第二党」ですが、支持率の急伸は台湾政治の流動性を示しています。無党派層が26%と大きいため、今後の選挙戦では 野党連合の形成 や 中立層の取り込み が鍵となります。
Copilotによれば、国民党が民衆党と連立を組み、政権に返り咲く可能性も可能性がかなり高い。そういう事態になれば、「台湾有事」になることはない。だから、「台湾有事は日本有事」とであり、「存立危機事態」になるから「自衛隊を派遣する」などと言うことは、「ピエロ」の域を出ない。その民衆党の対中政策について、チャットした。
民衆党の対中政策はどうなのか
結論: 台湾民衆党(TPP)の対中外交政策は、国民党の「融和路線」と民進党の「防衛強化路線」の中間に位置し、「現状維持」+「柔軟な対話」を基本としています。柯文哲前主席の方針を継承し、台湾の安全保障を確保しつつ、中国との経済・人的交流を維持する「バランス外交」を志向しています。
🧭 まとめ
民衆党の対中外交政策は、「現状維持」+「柔軟な対話」+「国際協力」を軸にしたバランス外交です。国民党の親中路線と民進党の防衛強化路線の間に位置し、台湾政治において「調整役」として重要な存在になっています。
次に、米国の対中政策についてチャットしてみた。
米国の対中政策はトランプ政権下で「曖昧政策」に回帰したのではないか。
結論: トランプ政権は台湾政策において、バイデン政権の「防衛明言」から一歩引き、再び「戦略的曖昧性」に近い姿勢へ回帰していると見られます。ただし、完全な後退ではなく、対中強硬派(注:戦争省のコルビー次官を指すと思われるが、同次菅自身も曖昧戦略を採っている)を政権に起用しつつも、トランプ自身は「ディール重視外交」によって台湾防衛を交渉材料化する傾向を示しています。
🇺🇸 トランプ政権の台湾政策の特徴
・曖昧性の復活
バイデン政権は「中国が侵攻すれば米国は防衛する」と明言しましたが、トランプは「武力併合阻止を維持するかどうか」について発言を避けています。これは従来の「戦略的曖昧性」に近い立場です。
・ディール重視外交
トランプは台湾問題を貿易や資源問題と絡めて「取引材料」とする姿勢を見せています。習近平が台湾独立反対の明言を迫る中、トランプは交渉余地を残している。
・政権人事は強硬派
国務長官にマルコ・ルビオ、国家安全保障補佐官にマイク・ウォルツなど対中強硬派を起用しており、政権全体としては中国抑止を重視しています。ただし、大統領本人の発言は一貫性に欠けます。
・台湾への圧力
トランプは台湾に「防衛費増額」を強く要求し、半導体産業を米国に取り戻すべきだと主張しています。これは台湾支援を条件付きにする姿勢を示しています。
トランプ大統領がこうした状態にあるのは、同大統領が世界の多極化を強力に推進しているからである。だから、高市首相も「反共右翼外交政策」とは完全に決別し、「多極化外交」に大転換する必要がある。ここから出てくる結論は、「米台関係は双方に委ねる」ということである。そうしてこそ、中国の意図を「aspect」つまり「尊重する」ということになるとともに、台湾からも信頼を勝ち得ることが可能になり、中台双方と戦略的互恵関係を結ぶことができるようになる。反共右翼外交のままでは、中国からの大反発が継続することになるし、台湾のサイレントマジョリティからも目をそむけられることになる。
なお、この高市発言について、国際情勢解説者の田中宇氏は「高市を助ける習近平」と第する解説記事を投稿・公開された(https://tanakanews.com/251116japan.htm)。本解説記事のリード文は次である。
習近平の中共は表向き、高市の日本と敵対し始めたが、実際は、中共が中国人の日本流入を止めてくれて、高市を助けている。中共は、高市を殺すぞと言いつつ、実は支援している。この展開はもしかすると、トランプが習近平に頼んでくれたのかもしれない。トランプと習近平が、英傀儡な日本外務省の抵抗を乗り越えて高市を救っている。
本文の一部を抜粋すると、次のようになる。
米諜報界はリクード系になり、英国系が自滅したのだから、もう移民や旅行者を受け入れる必要はなくなった。しかし、高市が外国人の流入を止めたくても、外務省や権威筋など英傀儡の残滓があれこれ妨害して転換を阻止する。外国人が来なくなると日本経済が破綻するというマスコミの歪曲報道も騒がしい。守銭奴な中国人の喧嘩腰の値引き要求を受け、インバウンド担当の日本人の店員たちは疲弊している。人道問題なのにマスコミは無視している。為替を円高にすれば外国人が来なくなるが、米国(英国系からトランプまで)が望む株高のために円売りドル買いして資金供給せねばならないので無理だ。
早々と万策尽きたところに、意外な助っ人が現れた。それが習近平の中共だった。中共は今回、日本乗っ取り策の基盤となっている中国人の日本への移動を「危ないから行くな」と言って止め始めた。日本の流入する外国人の多く(最も有害な部分)を占める中国人が来なくなる。習近平の中共は表向き、高市の日本と敵対し始めたが、実際は、中共が中国人の日本流入を止めてくれて、高市を助けている。中共は、高市を殺すぞと言いつつ、実は支援している。表と裏が真逆な中国外交。孫子の兵法。元寇以来の逆神風。この展開はもしかすると、トランプが習近平に頼んでくれたのかもしれない。トランプと習近平が、日本外務省の抵抗を乗り越えて高市を救っている。とか。
中共は、実は日本の右傾化を歓迎しているのか??。そんなわけない、とみんな思うだろう。だが、日本が、人道主義を振りかざして中国包囲網を維持する英国系の傀儡国から、こっそり中露と親しい隠れ多極派であるトランプの傀儡国に転換するなら、それは習近平にとって望むところであるとも言える。
いずれにしても、高市早苗首相か旧態依然とした「ウクライナへの経済・軍事支援を含む反共右翼外交」から「多極化推進外交」に大転換することだけが、事態の沈静化と日中関係の安定化と戦略的互恵関係の深化につながる。トランプ大統領はもちろんプーチン大統領、習近平主席、ネタニヤフ首相、サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマーン・アール皇太子兼首相兼経済開発評議会議長、モディ首相ら世界の大物政治家と直接会い、国際情勢の地政学的実情を肌で実感することが大切だ。