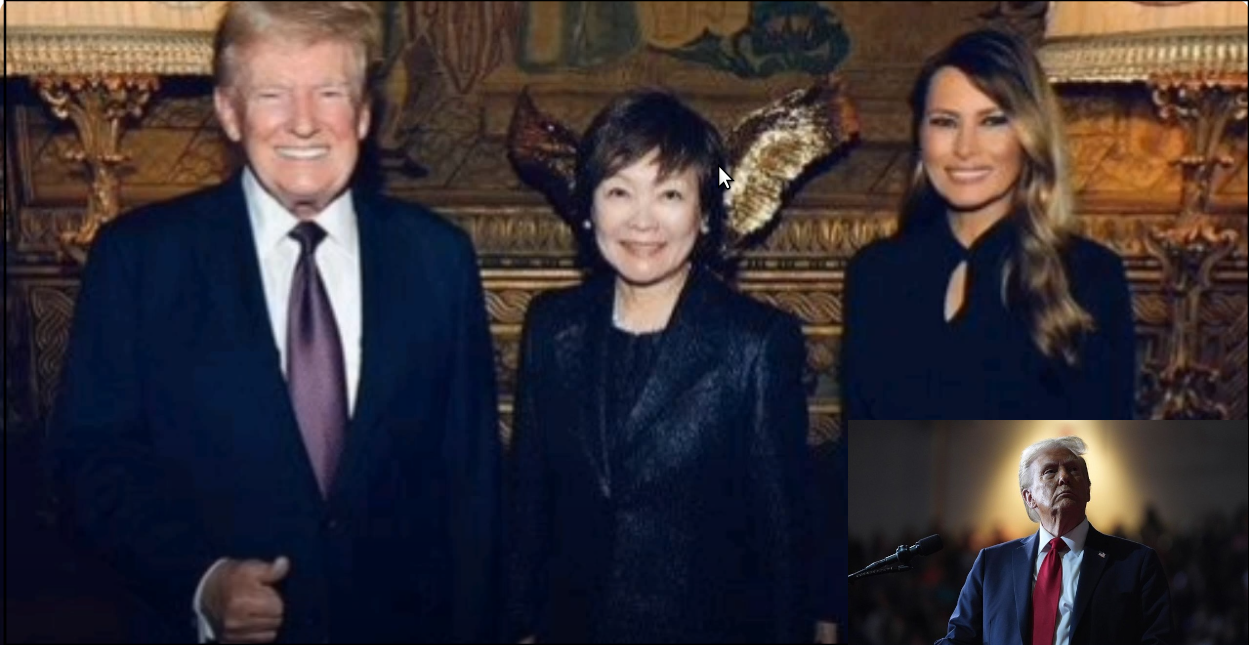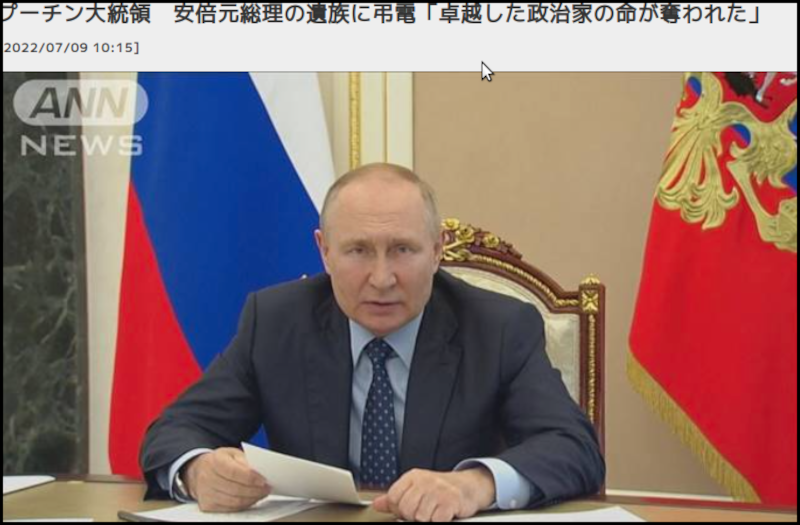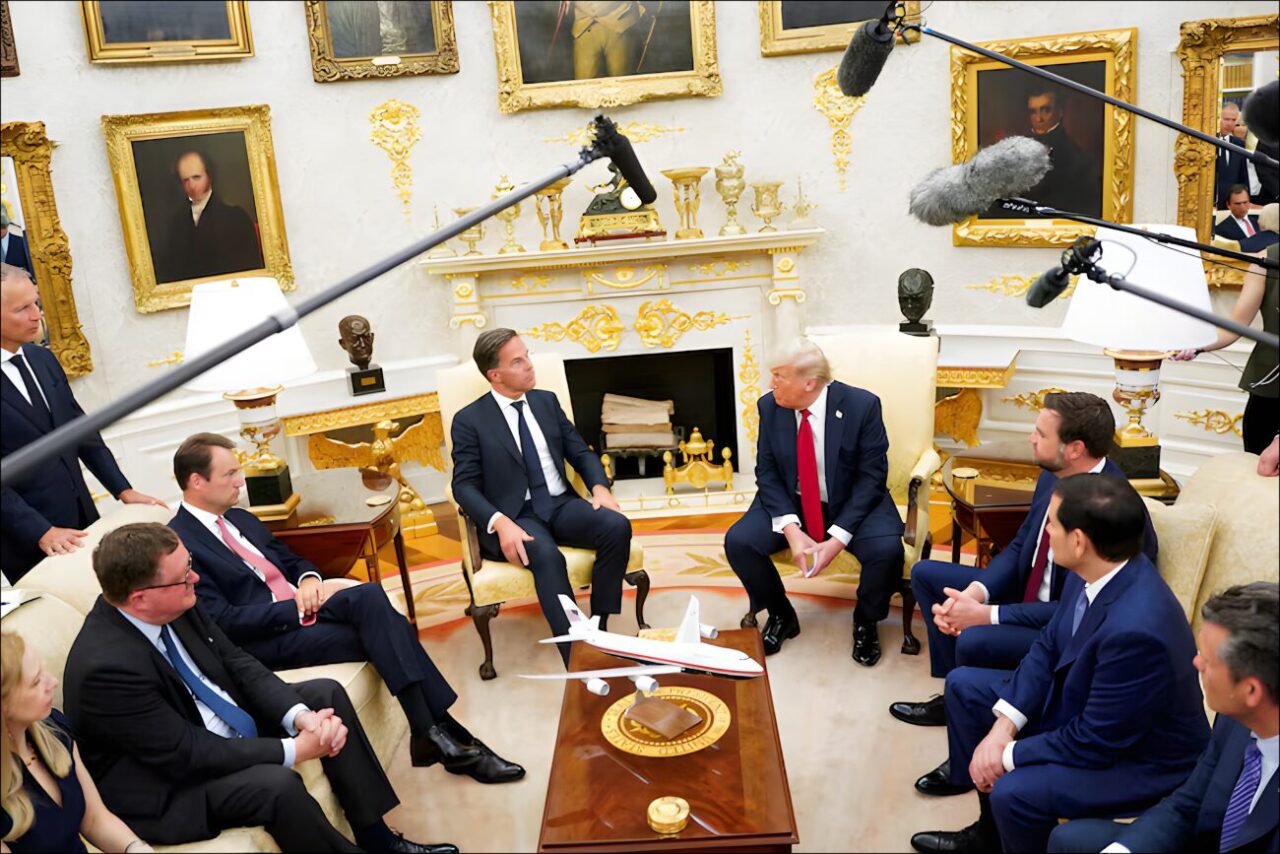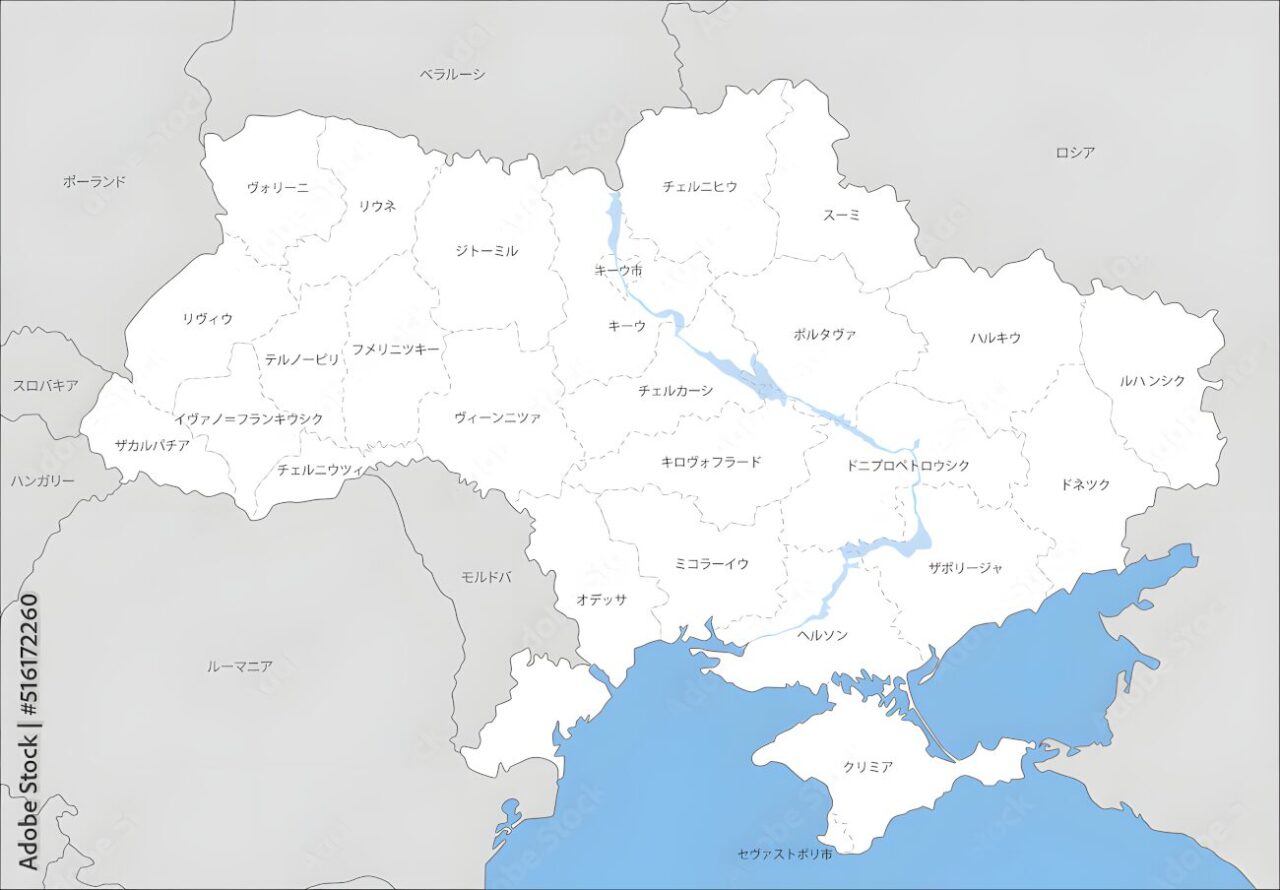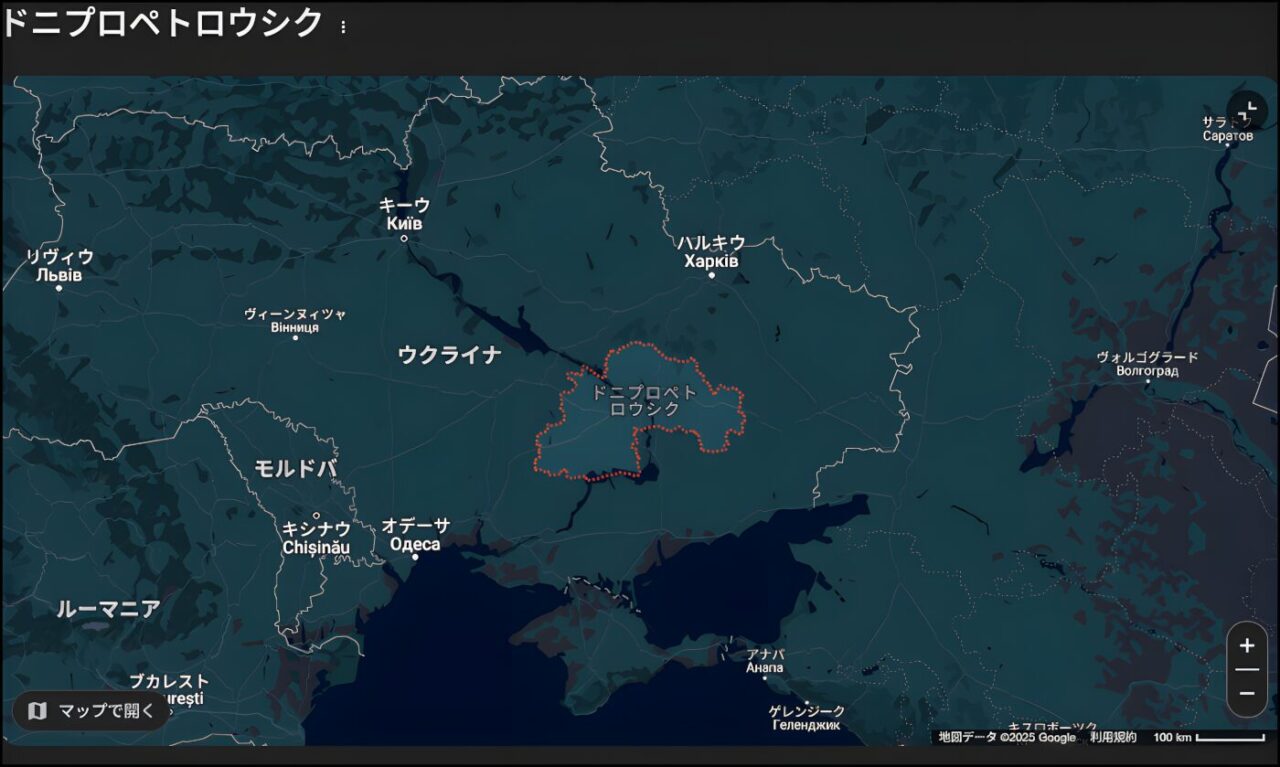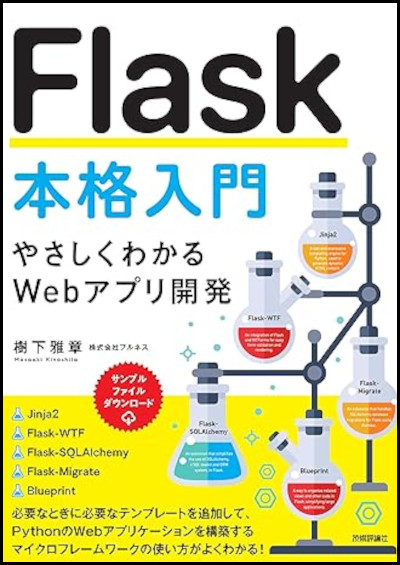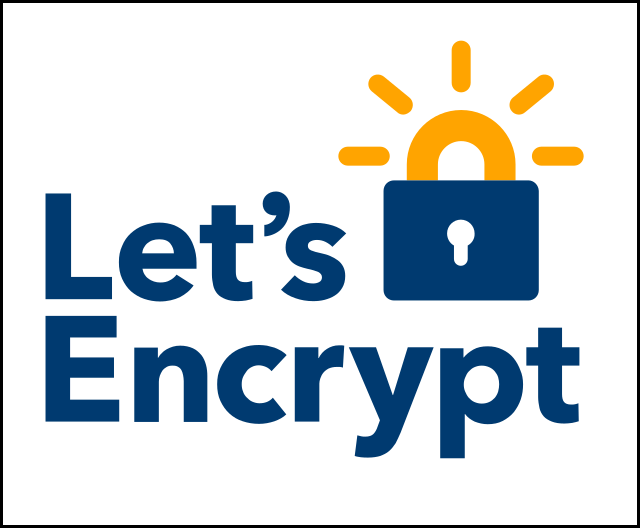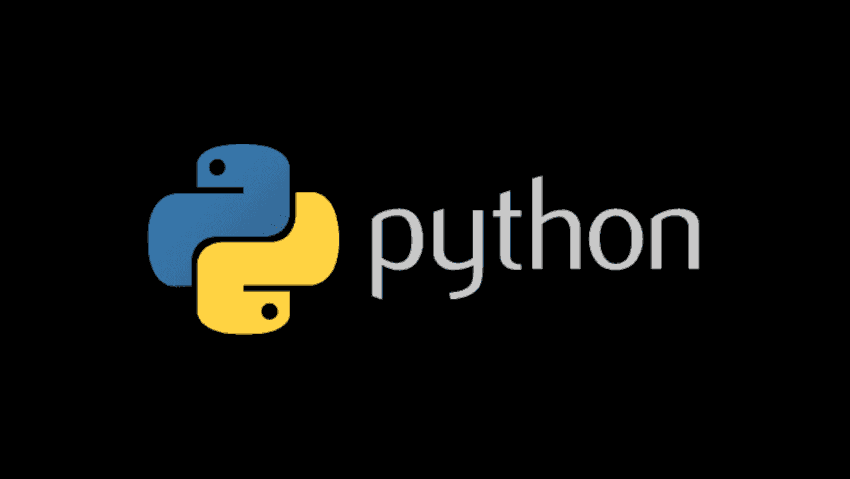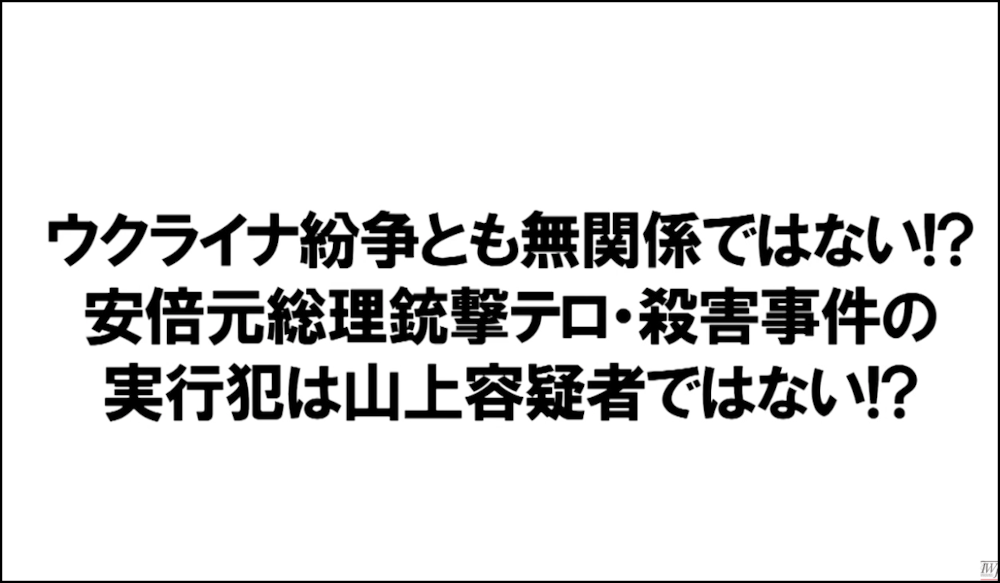日本一新の会・代表 平野 貞夫妙観
〇 私の「共産党物語」 8
(共産党が議会政治体制内政党に変わろうとするこれまでの経緯)
毎回理屈っぽい話ばかりで恐縮だが、参議院選挙を目前にして、共産党の創造的変化に対し、自公与党は敵愾心をもって国民に誤解を拡大させる活動を強めている。民進党の中には共産党を利用しても、仲間として認めたくないという輩が多い。その結果、7月10日の参議院選挙では「部分的野党協力」しかできなかった。これが我が国の議会政治の現実だ。
真の「議会民主政治」を確立するには、まず全員ではなくとも「自立した有権者」が適切な人数存在すること。社会の木鐸としての魂を忘れないマスメディアが数社あればなんとかなる。官僚組織の健全性も大事だが、しっかりした有権者が、しっかりした代表者を選べばなんとかなるが、それが実現しないのが日本の悲劇だ。
昭和30年、1955年から始まった「自社55年体制」は、事実上共産党を排除した「日本型談合政治」であった。平たくいえば、国会審議では厳しい対立、時として物理的抵抗を繰り返したが、その多くの場合裏ではしっかりと手を握るシナリオが準備されていた。政策的取引が行われるのならともかくも、自民党から国会対策費として、事実上のワイロが介在した。
共産党は昭和30年代後半には、ソ連や中国共産党などの影響を避けるという「独立路線」を選択するようになる。そうなると国内での活動戦略は、議会主義体制内に入らざるを得ない。しかし、自社55年体制の談合議会政治の中に入るわけにはいかず、孤高の正論の中に生きる道を探していく。一方、「60年安保」を契機に社会党右派の一部が離党して「民主社会党」を結成する。
大企業労組の支持を受け、自社体制より自民党側を有利にする動きとなり、官公労中心の社会党と距離ができる。公明党は、昭和31年(1965年)に参議院全国区に3名を当選させ、国政に進出する。創価学会という宗教団体を母体とし、
平和・福祉・人権の確立を理念とした。衆議院という政権を争う場には進出しないと国民に公言していたが、なんと、昭和42年1月の総選挙で25名を当選させて衆議院に進出する。
国会の政党構造は、「自民」対「社公民」といっても、社会党に引っ張られた「公民」は、社会党の「金魚の糞」であった。公明党の衆議院進出で変わった政治状況は、共産党との選挙で血を流すような争いであった。両党とも貧困層の未組織有権者に支持を求めたことによる。
昭和44年には、創価学会と公明党の「出版妨害事件」が発覚する。これにより創価学会は憲法上致命的な傷を負うことになる。この時期、共産党は「愛される共産党」をキャッチフレーズのもと、敵対する勢力との修復を戦略とするようになる。昭和47年の総選挙で公認候補を38名当選させ衆議院で野党第2党となり、自社55年体制の枠外で、孤高の正論を楽しんでいる時ではなくなった。そこで共産党が選んだ戦略は、創価学会との友好関係を盟約すること。国会改革を要求して議会政治体制内政党として、国民に理解してもらうことであった。
昭和49年に「共創協定」が結ばれたこと、同年に国会の国際行事で「天皇陛下のために乾杯」を容認したこと、国会改革で、「棄権の権利を国会法に明記せよ」との要求、などは偶然の動きではない。
(共産党が要求した「棄権の権利を国会法に明記せよ」の顛末)
(続き)
昭和49年から本格化した「議会制度協議会」では活発な意見が党派を越えて出るようになり、その中で注目されたのが共産党の「棄権の権利を国会法に明記せよ」であった。これには前尾議長が理解を示し、私に非公式に検討するよう指示があった。私は「共産党がレーニンの理論を誤解したのか、利用したのか、この主張を続ける限り議会主義政党とはいえない」と前尾議長に主張すると「君は共産党となると理屈っぽくなる。レーニンの理論をよく調べて、引用に誤りがあれば、東中議運理事に(議会制度協議会担当)にそれとなく話して、共産党から要求を取りさげるようにするのが政治だ」と説教される。そこで私は、法政大学大学院時代に全国の大学で唯一「社会主義国家論」という講座があり、そこで教わったロシア語に精通した飯田貫一教授に会いに行った。
レーニンの議会論について意見を聞くと、レーニン全集の原文を調べてくれて「レーニンは棄権を奨めていない。やむを得ず棄権する場合には、国民に誤解の無いようよく説明しろ」と理解すべきだと教えてくれた。早速、東中議会制度協議会担当に会って、「レーニンの論文引用に問題があるのではないか」と説明というよりも反論になり「何をいうか」となる。共産党の組織の絶対性を感じ、自社55年体制の談合政治も問題だが、共産党が議会政治体制に入るには暫しの時間を要すると思った。
(続く)
〇 ようやく議論となった「憲法九条の法源」
月刊誌『世界』7月号に、柄谷行人―大澤真幸両氏による「対談 もうひとつの謎〝憲法の無意識〟の底流を巡って」が掲載されていた。4月に柄谷氏が『憲法の無意識』(岩波新書)を刊行し、それを補完するための対談といえる。岩波流の「隔靴掻痒」ともいえる憲法観に若干の抵抗があったが、憲法九条を哲学的心理学から論じた点は評価したい。
昨年の安保法制問題で、日本中が騒然となっていたとき、私は憲法9条の法源を深層心理学者ユングの方法論で、日本人の約310万人の第2次大戦犠牲者の「霊的集団無意識」を日本人の感性が受けとめていたことにある、と考えていた。この考え方をその後反省、第1次・第2次大戦での世界中の戦争犠牲者、約3千万人(この数字は直接生命を失った犠牲者の推定で間接的犠牲者を入れると7千万人を超えるといわれている)の「霊的集団無意識」を日本国憲法九条の立案制定過程で世界の指導者も受けていた。これを日本人が心の奥底、無意識(柄谷氏が言う「超自我」)に定着させたことにあると思うようになった。
この私の考えは、高知勝手連をはじめ、このメルマガでも論じてきたが、哲学者・柄谷行人が岩波新書や『世界』で、同じ流れで論じるようになったことに敬意を表したい。私との違いは柄谷氏がフロイトの心理学を参考としていることに対し、私はその弟子であるユングの深層心理学を応用していることだ。その結果、私は「霊的集団無意識」という言葉を平気で使う。柄谷氏は「人間の思考は人間による判断」という、デカルト・カントの近代文明の枠内の学者であり、口が裂けても「霊的」ということばを使わないことによると思う。
柄谷氏は、かつて憲法9条について次のように語っている。「まさに日本の権力にとって『強制』でしかなかったこの(9条)条項は、その後、日本が独立し簡単に変えることができたにもかかわらず、変えられませんでした。大多数の国民の間にあの戦争体験が生きていたからです。しかし死者たちは語りません。この条項が語るのです。それは、死者や生き残った日本人の『意志』を超えています。もしそうでなければ、何度もいうように、こんな条項はとうに破棄されているはずです」
どうして哲学者や憲法学者は、人間の死をこのように無機質化するのか、もっと素直になってもらいたい。私には戦争で生命を落とした死者たちの声が聞こえる。第1次・第2次大戦で生命を落とした約7千万人の犠牲者の「霊的無意識」が、日本国憲法に9条の規定を入れ、それを「戦争放棄」の法源として無意識に受け入れた日本人の人類史的宿命と思う。さらに、第2次大戦後の直接・間接に生命を失った犠牲者は3千万人を超えるといわれている。わずか100年で、人類は戦争で1億人という生命を失っている事実をどう考えるか。
柄谷氏は「日本人が憲法9条を護ってきたのではない。憲法9条が日本人を護ってきたのだ」と語り、「憲法9条が我々の方にやってきたのだ。あるいは、神がそれを送ってきたのだ」とも語っている。その通りだ。
問題は9条(戦争放棄)の日本での先行形態を、徳川体制にあるというユニークな論を展開していることだ。「戦争放棄」とは軍事活動だけのことではない。「人間の生存権のあり方」のことである。その意味で、先行形態を徳川体制と断定するのは問題である。数年前、日本一新の会の会員にも協力を仰ぎ、「国際縄文文学協会」で柄谷氏の話を聞いたが、「縄文時代の日本人の感性」に憲法9条の先行形態がある、というのが私の主張である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次回の定期配信は、6月23日(木)です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━END━━━━━