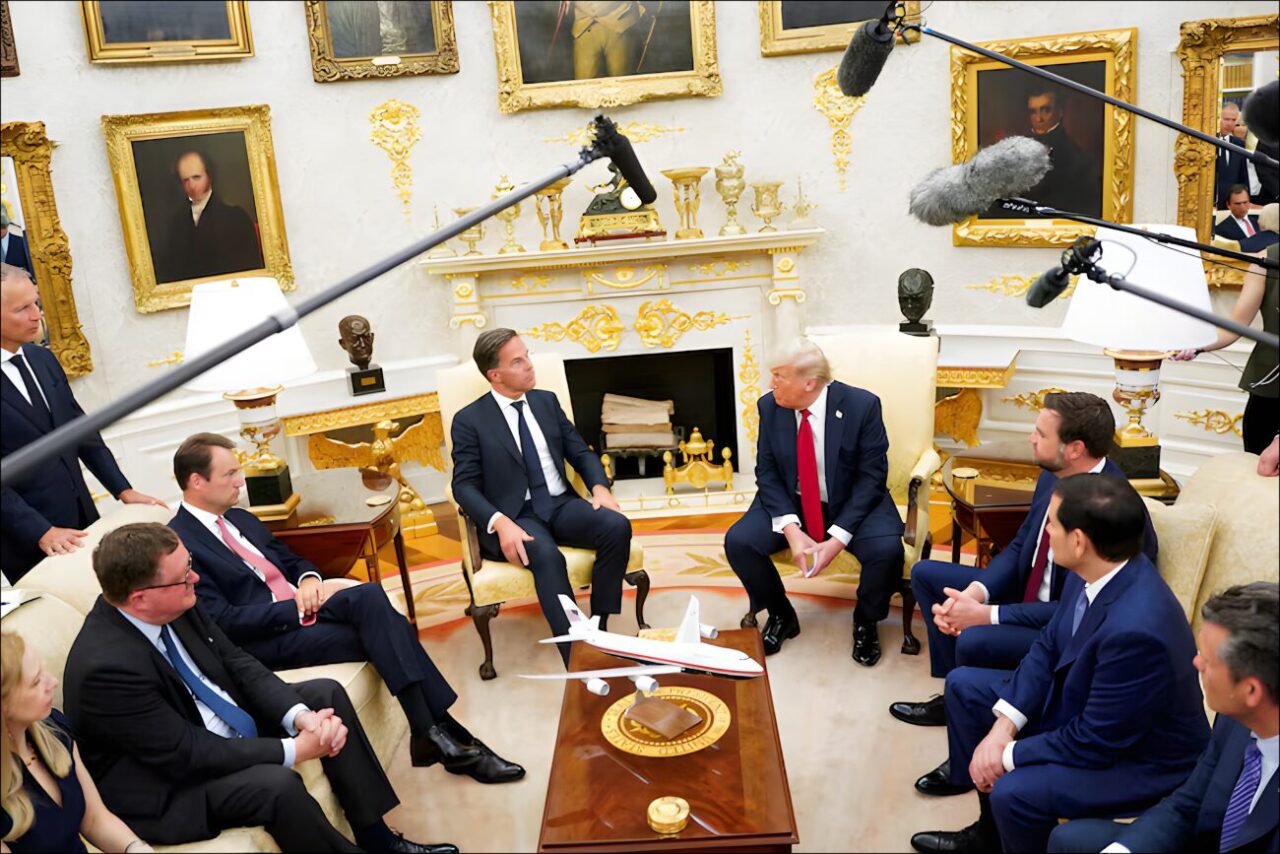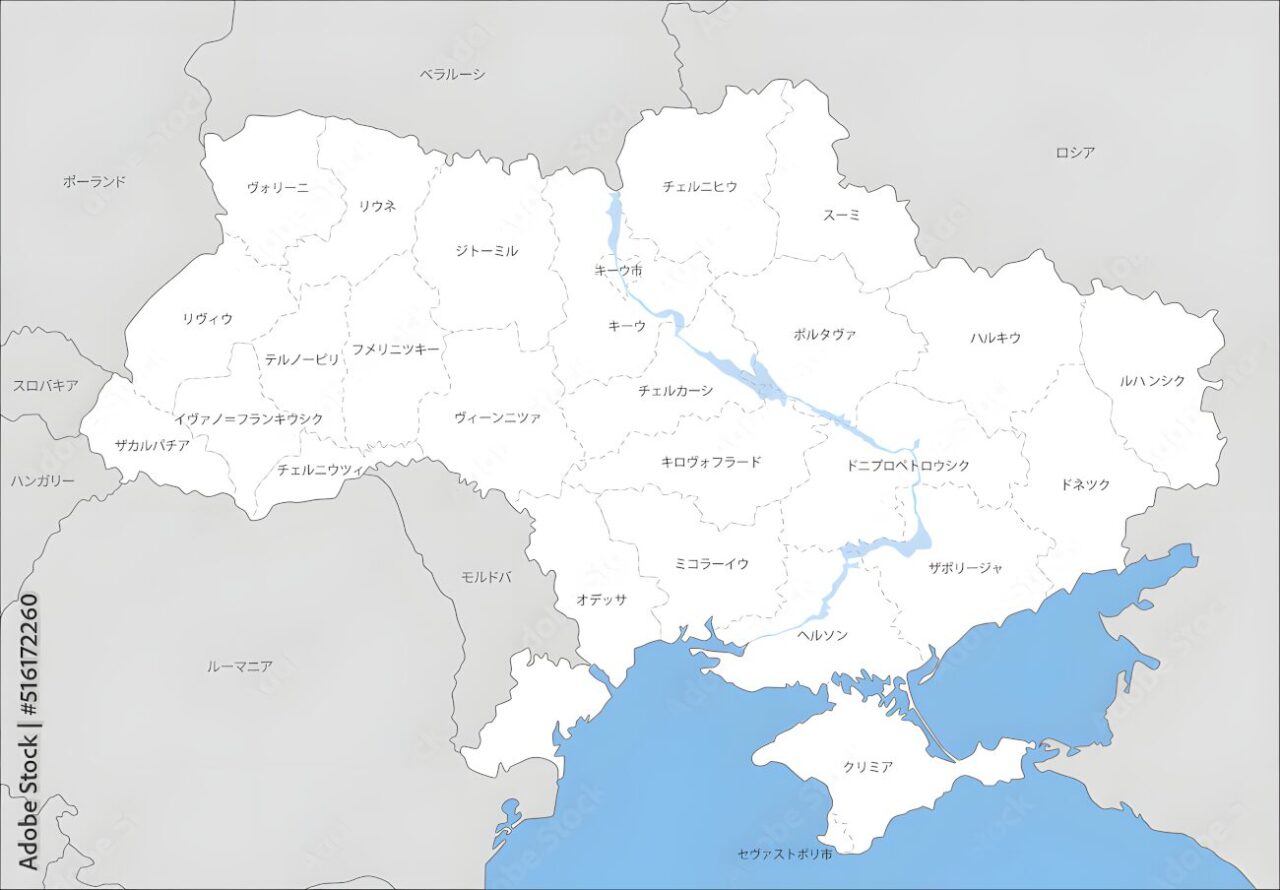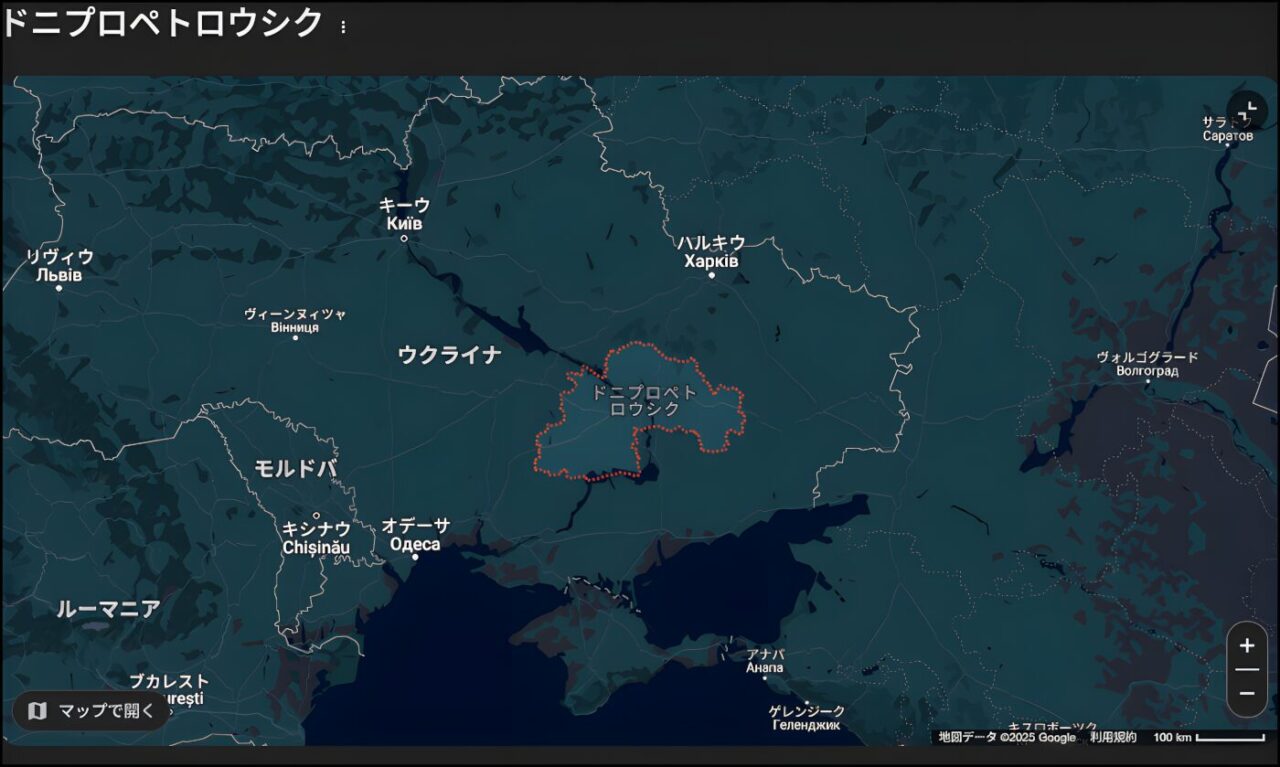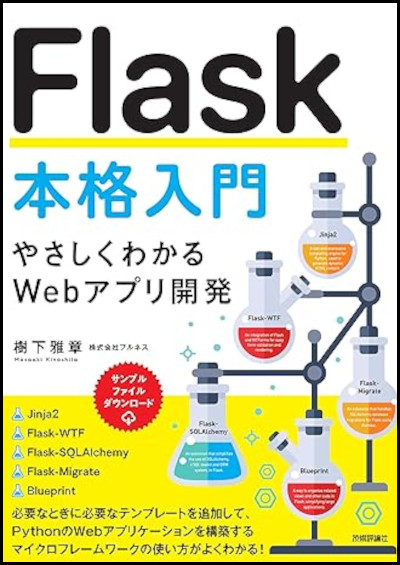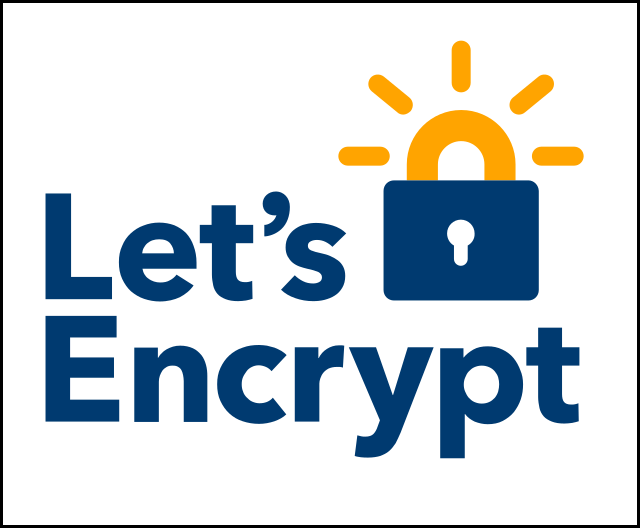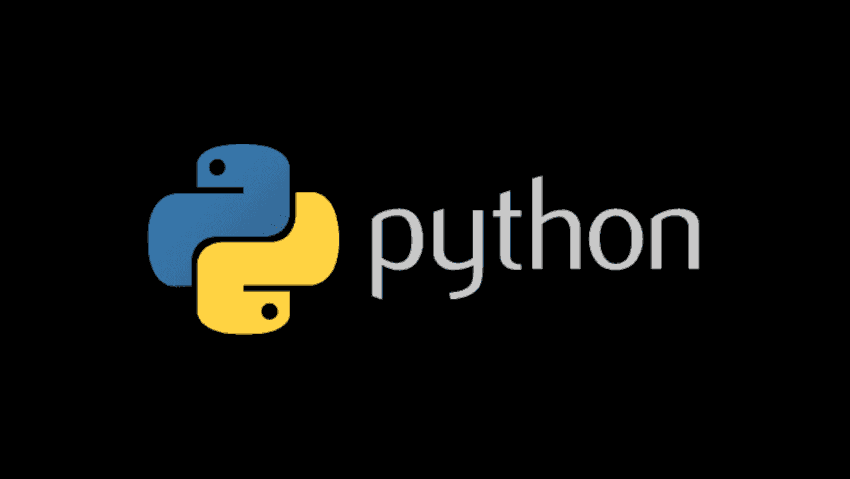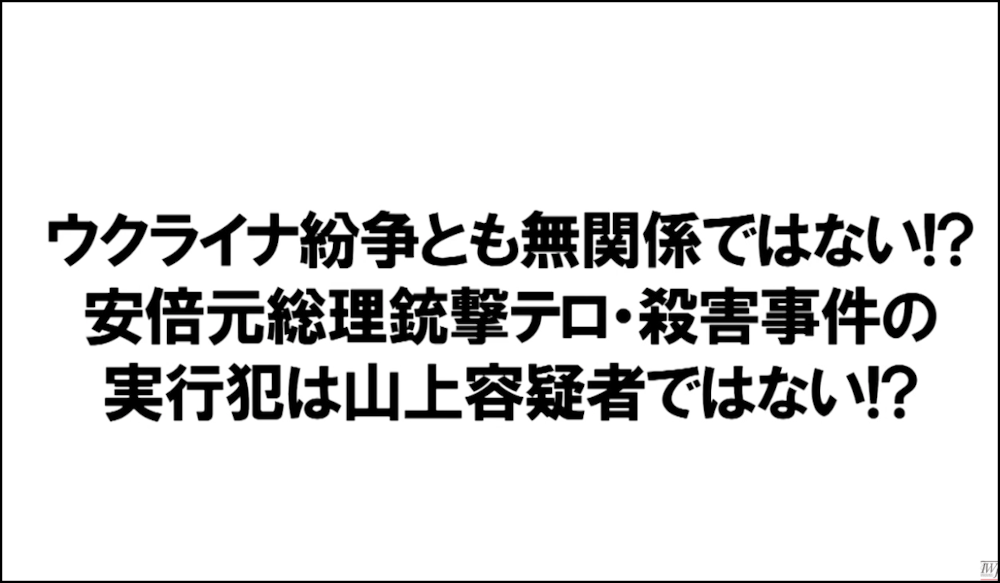日本一新の会・代表 平野 貞夫妙観
(安倍首相の悪政の始まりはオリンピック招致での放射能対策への嘘言演説にあり!)
安倍首相はえらく〝アベノミクス〟に自信を持っている。自分で衆議院解散の名称に「アベノミクス解散」と記者会見で公言した。自分の名前を解散名にするとは恥知らずでは済まされない。ひょっとすると公職選挙法違反になるかも知れない。病院で精密検査の要がある。
野党も解散名をいろいろ言ってはいるが、それぞれに、手前の都合でのことだ。問題は安倍政権の悪性が何時から始まったかだ。本質論をいえば、このような人物が政治的リーダーのトップになるという日本デモクラシーの性格というか、構造こそ検証しなければならない。この際、それは脇に置くことにして、現実的に安倍政治は何時から、どうして狂ってきたか、検証することから始めたい。
安倍政治は、平成24年12月に成立して、同25年7月の参議院選挙までは、甘く見ても慎重な政治運営と政策展開を行っていたといえる。悪政の始まりは9月初旬の東京オリンピック招致の際に福祉第一原発事故に対する国際公約の嘘言からだといえる。安倍首相は「状況はコントロールされている。まったく問題はない。汚染水は原発の港湾内0・3平方キロ範囲内で完全にブロックされている。近海も問題ない。食品・水・健康も現在、将来とも問題ない。私が責任を持つ」と発言した。
これは昨年9月8日、IOC総会でのオリンピック招致演説と、質問に対して、日本国の総理大臣として世界に約束したものだ。1年3ヵ月を経て、安倍政権は何をしてどんな成果を得たのか。念願のオリンピック招致には成功したものの、「IRIO」という汚染水対策への研究機関をつくって形式だけの〝努力〟に終始している。ここでは詳しいことを割愛するが、「福島第一原発の状況は、ますますコントロールできず、問題はより深刻になった」ということである。
汚染水対策の切り札といわれた「凍結止水壁」に失敗し、東電は11月21日に原子力規制委員会で凍結止水の断念を表明した。最近では米国の西海岸で福島第一原発事故によるセシウムを含む汚染水が採取されたとの報道があった。現時点では人体に影響ないとのことだが、発生源が放置どころか、最悪の状況に向かっているのだ。今後、国際的問題に発展することは必至であり、もし、補償問題に転化したら大変なことだ。
国内での放射能対策も深刻さを増している。福島県の実状は放射能問題の風化政策ばかりである。首都圏での放射能問題は情報が隠されており、海外の主要なジャーナリストから何時報道されるかわからない情況である。そんなことになれば、東京オリンピックどころではなくなるのだ。私が得た情報によると、安倍政権は福島第一原発事故処理について、すべて米国に丸投げする方策を、某シンクタンクに立案させているとのことである。恐らくは、米国に丸投げすることで、安倍首相は「状況をコントロールするために、米国の技術を信頼して欲しい」との言い逃れをするつもりだと、私は推測している。
(何故、ナノテクによる放射能提言研究を本格化させないのか)
本年2月私は『戦後政治の叡智』(イースト新書)を刊行した。終章で「福島第一原発問題を解決し、東京五輪を新たな文明の出発点へ」を執筆しておいた。そこには私も参加している「ナノ純銀による放射能低減システム研究会」の研究成果を発表している。要点は「セシウムの半減期は、約30年間といわれているが、それを約1~2ヵ月程度に短縮する」という実証実験の結論である。これは「低エネルギー核反応」(ある種の常温核融合)であり、「核種変換」の可能性がある。
これは学会に発表されている学説として確立している。米国をはじめ、各国で3・11以来急速に研究が始まっている。また、類似の研究が三菱重工やトヨタ中央研究所で行われたと報道されている。私たちは、第三者による再現実験と「核変換」でどのような物質に変化するか、確認実験を再三再四にわたって要望している。この研究が成功すれば原発不用の新しい文明をつくることができるからだ。しかし政府も学会もそして企業も無関心である。既得権で支えられている現政権や学会、電力会社にとっては排除すべき研究であるからだ。
○消費税制度物語 (2)
歴史上初めての敗戦を経験した日本が、あの惨状のなかからの復興と、世界の奇跡といわれる豊かな社会を実現できたのは国民のひたいに汗するひたむきな努力と、適切な「税務政策」であった。その歴史を簡単に振り返ることから始めたい。
(シャウプ勧告)
敗戦直後の混乱期を乗り切った我が国は、GHQの指導により、戦後の税体制を確立すべく、昭和24年9月にカール・シャウプ博士が来日して、「シャウプ勧告」が作成され、それによる税体系が実行された。要旨は、
1)国税・地方税を通じ、税制全体として直接税を中心として税体系を構成し、間接税を軽減または廃止する方向をとった。
2)所得税・法人税・相続税を近代化し大幅な改革を行った。
(例・所得税最高税率を85%から55%に引下げ、法人税を35%に一本化した)
3)租税特別措置を厳しく合理化した。
4)地方税の付加税主義を全廃し独立税主義とした。市町村税として固定資産税を設け、また地方平衡交付金制度を創設した。
5)所得税・法人税に青色申告制度を設け税制上の恩典を与えることにした。
等々である。この「シャウプ勧告」は、我が国の税制史上画期的な提案であった。昭和25年の税制改革において、勧告内容の多くが実現された。
(経済成長に伴う戦後税制の改革論議)
昭和31年の経済白書は「もはや戦後ではない」と述べ、さらに昭和35年には国民所得倍増計画が策定され、高度経済成長政策が浸透する。その過程で、昭和40年の金融引き締め政策を契機に経済成長が低下し、並行して税収の伸びが低下、同年度補正予算で赤字補填公債を発行せざるを得なくなった。
昭和40年代後半には、ニクソン・ショック、石油危機、そして為替の変動相場制への移行と、我が国の経済は国際経済の荒波のなかに置かれた。それからの事態打開のための緊急対策、さらに福祉国家実現のため歳出は膨張し税収とのギャップが拡大した。またこの時期、物価対策や不況対策などで所得税減税が行われていた。昭和50年不況で歳入欠陥となり、補填のための赤字公債の発行が始まり、いわゆる財政危機の論議が本格化する。このような状況の下、抜本的税制改革の必要性が各界から提示されるようになった。
国民生活からいえば、累進構造の所得税は、所得水準が平準化すると、税の公平な負担が確保されなければならない。経済の変化の中で、「十五三」とか「九六四」といわれる(課税所得の捕捉率が給与所得は十(九)割であるのに対して、自営業は五(六)割、農業は三(四)割程度であるという意味)、中堅サラリーマンなどを中心に納税者の重税感が高まり、不公平感が著しく高まってきた。さらに人口の高齢化、消費への価値観の多様化、グローバル化など従来の税制のままでは対応できなくなった。こうした経済・社会状況下で、シャウプ勧告に基づく戦後税制の改革論議が活発化し、一般消費税の導入論へとつながる。
(一般消費税導入論の提起)
一般消費税の導入について、政府側から最初に問題を提起したのは当時の福田赳夫大蔵大臣である。昭和45年3月で「直接税負担を軽減し、財政需要に応ずるという二つの面から間接税を増税したい」という発言であった。翌46年には政府税制調査会で、「EC型付加価値税を中心に検討すべき」との意見が出るようになる。
この時期、政界でもっとも熱心に消費税を研究し、導入を主張していたのが敗戦直後の大蔵省主税局長で、駐留軍と増税問題で苦労した前尾繁三郎氏であった。前尾氏は昭和48年5月から、51年12月まで衆議院議長に就任しており、私は秘書役を務めていた。朝から晩まで時間のあるときは、福祉社会のための消費税導入の話を聞かされた。議長に就任して6ヵ月目のころ、議長公邸にキャッシュレジスターを持ち込み「消費税が導入されたら、こんな使い方になるのか」という熱心さであった。
(続く)