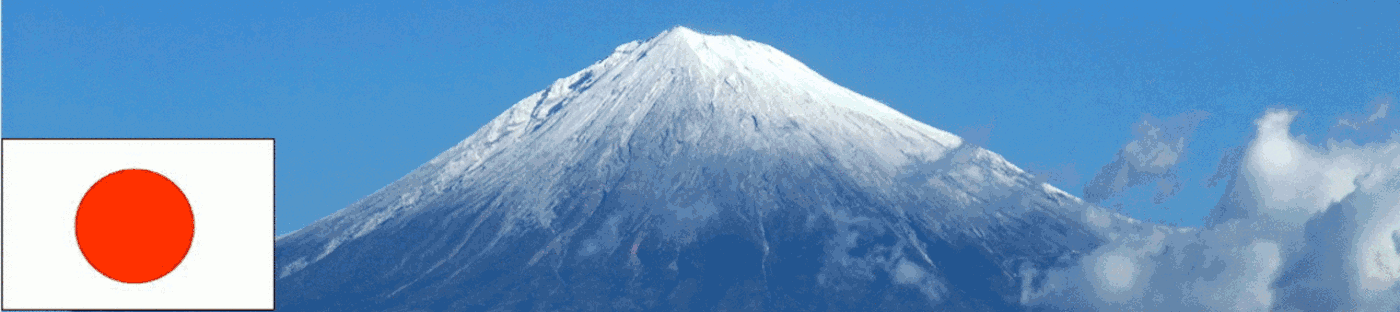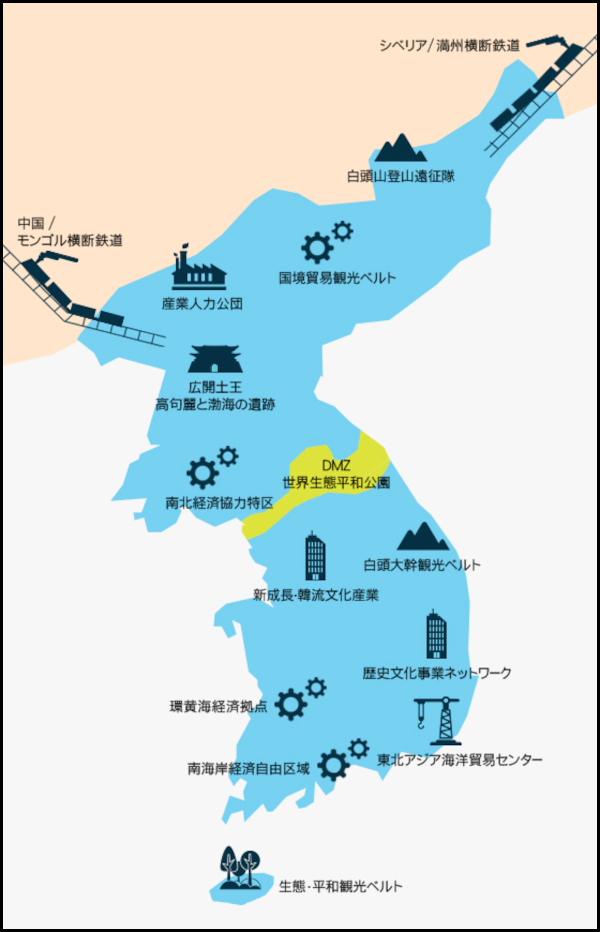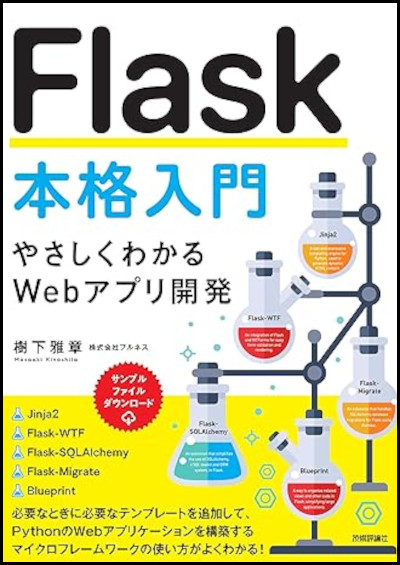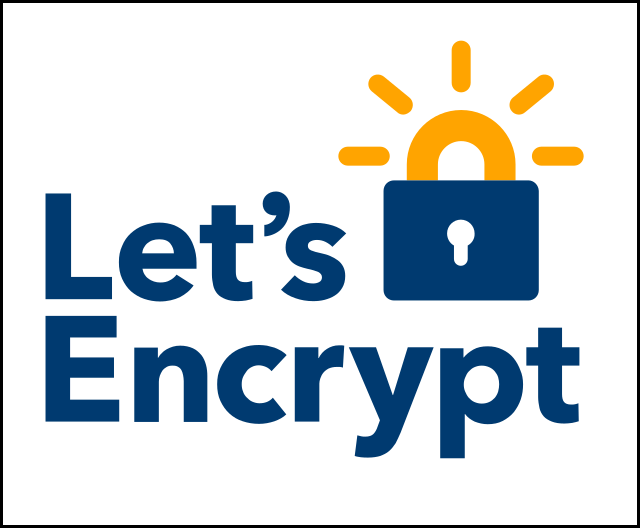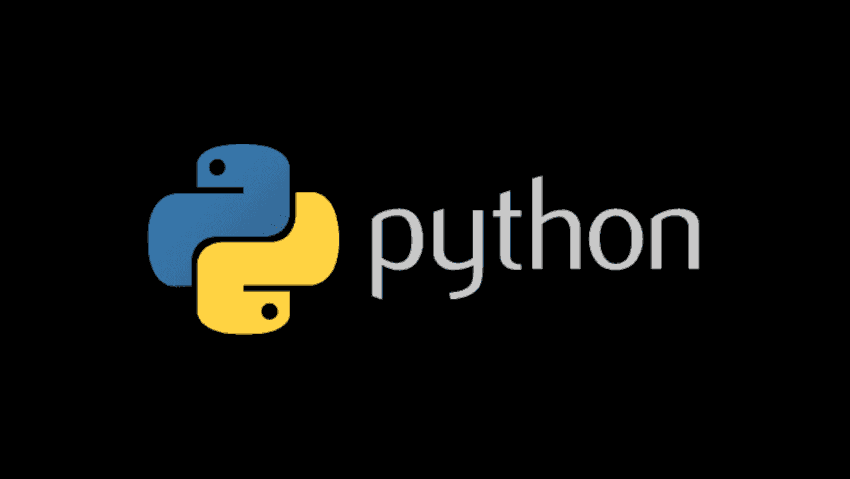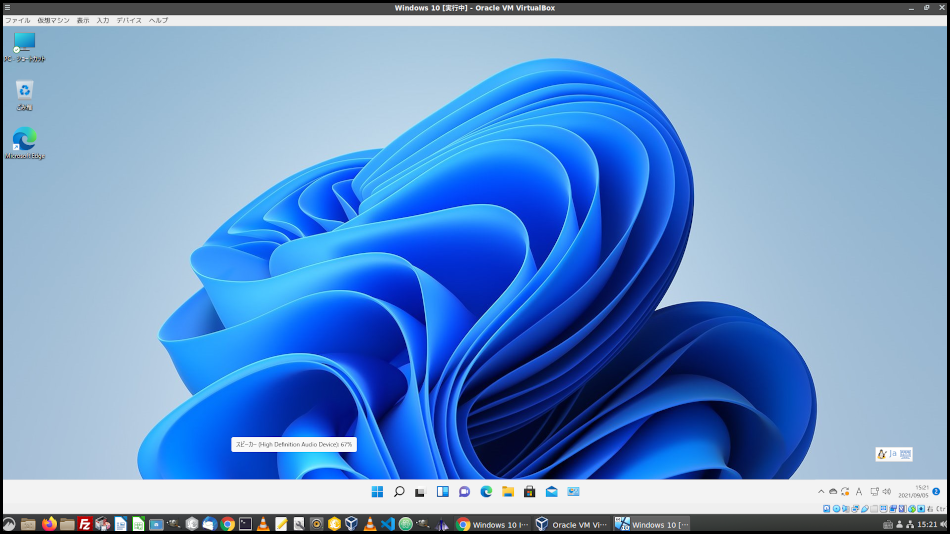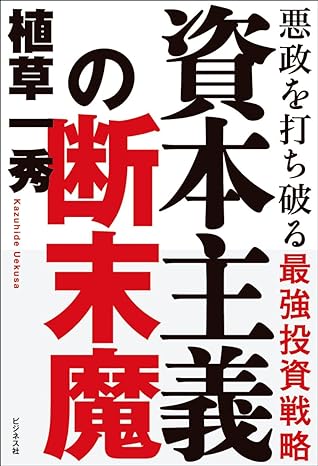韓国人元徴用工裁判で韓国大法院が2018年10月30日、新日鉄住金に対し、大阪、釜石、八幡の製鉄所と清津の製鉄所建設に強制動員された韓国人被害者4人に対し、1人当たり1億ウォン(約900万円)の損害賠償を認める判決を確定させて以降、日本の安倍晋三政権は韓国を貿易制裁措置であるホワイトリスト国が外す対抗措置を取り、一方の韓国は軍事情報に関する包括的保全協定(GSOMIA=ジーソミア=)の破棄を通告する(現在は延期)など、日韓関係は悪化の一途を辿っている。どう、日韓関係を改善するのか、探ってみた。
1月20日から開会した通常国会では幾多の疑惑に対して誠意ある答弁を見せない安倍晋三首相であるが、その件に関しては別項で述べる。
本題に戻り、日韓関係が改善しないのは、日露戦争終結後の1905年(明治38年)11月17日に大日本帝国と大韓帝国が締結した第二次日韓協約=乙巳保護条約(いっしほごじょうやく)以降の日韓近現代史の解釈が、両国で完全に整理されていないことが背景にある。韓国は同条約以降、「大韓帝国(当時)は日本の植民地国と化し、日本の統治の圧政に辛酸をなめてきた」との認識であるのに対し、日本の戦後の歴代政府はこれを認めたがらない。そのために、徴用工問題や従軍慰安婦問題などの懸案事項が未解決のままであり、誠意をもって解決されていない。

韓国最大法院に向かう朝鮮半島出身の元徴用工ら=2018年10月30日、ソウルの大法院
これを受けて、日本の裁判所側から元徴用工裁判問題に終止符を打とうとしたのが、2007年4月27日に最高裁が判決を下した西松建設強制労働損害賠償裁判である。この最高裁判決は、➀個人の請求権は確かに存在する②しかし、サンフランシスコ平和条約の枠組みは「個人の請求権を裁判で解決すると、関係国と国民に大きな負担を負わせ混乱が起きるかも知れないから、個人の請求権は裁判で請求できないことにする」との判断に立っている③日中共同声明もこの枠組みにあるため、中国国民個人も裁判で損害賠償や慰謝料を請求できなくなった④個人の請求権については、中国人被害者と当該被告企業との和解で解決を図ることは差し支えない-との判断を下した。この判決に基づいて、西松建設は株主訴訟を起こされることなく、原告側と和解交渉を行い、和解が成立した。
この最高裁判決に対して本書の著者である弁護士らは、➀サンフランシスコ平和条約のどこにも「個人の請求権については裁判で請求することはできないとは記載されていない(原爆裁判では原告被害者が日本政府相手に訴訟を起こした)②中国や韓国もサンフランシスコ平和条約には参加していない③日中共同声明では「(損害賠償請求権を)放棄する)」の主語は中華人民共和国政府であり、中国の国民の請求権を放棄するとは一言も書かれていない。
さらに、日本が批准している世界人権宣言の第10条や国際人権規約(自由権規約)の第14条では、日本は個人の人権の尊厳を守るため、裁判を受ける権利を保障する国際法上の義務を負っていると指摘し、権利があったとしても裁判では請求できないという最高裁の判断は、人権尊重の戦後の歴史的風潮と真っ向から対立すると批判している。
しかし、最高裁判決で損害賠償、慰謝料請求を裁判所に提訴することは否定されたため、これが韓国人元徴用工の裁判にも適用され、韓国人被害者の請求権も日韓請求権協定で裁判では請求できなくなったとして、すべての日本での裁判で原告側が敗訴するようになった。こうした経緯から、日韓請求権協定については2007年4月27日の最高裁判決を堺に日本政府の解釈が180度転換し、➀2007年以前は裁判での解決を容認②2007年以降は裁判に訴えることは認められず、当事者間で解決すべき問題-ということになった。
これは、事実上、行政の支配下にある最高裁判所が日本政府の意向を忖度したものであろう。砂川事件で自衛隊は意見との判断を下した伊達秋雄裁判長の判決(伊達判決)が跳躍上告により差し戻しになり、結局は同判決が覆されたのも、米国政府の意向に沿って動いたダグラス・マッカーサーⅡ世の日本政府に対する暗躍があり、その米国側の指示に基づいて日本政府が最高裁に働きかけたことは周知の事実である。日本国憲法第79条は、近現代国家の基本原理である三権分立の理念からは大いに問題がある。
ただし、さすがの日本国政府も元徴用工被害者個人の請求権が消滅してはいないとの解釈は変えていない。ただし、元徴用工被害者と加害者企業との和解を積極的に勧めているとは言い難く、むしろ、第二次安倍晋三政権下ではそうした動きを阻止しているように見える。企業も加えて、経営陣が「株主訴訟」で訴えられることを恐れ、消極的のようだ。この結果について、韓国側はどのように対処したのか(続く)。

 |
 |
1 2